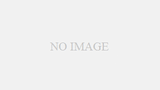「Goose houseって今どうなったの?」
そんな疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。かつてYouTubeを中心に圧倒的な人気を集めた音楽グループ・Goose houseは、2018年を境に姿を変え、**新たな形態「Play.Goose」**として再始動しました。
この記事では、その変化の背景や現在のメンバーの活動、そして彼らが挑戦している新しい音楽のかたちについて、わかりやすく解説していきます。
なぜ変わった?Goose houseからPlay.Gooseへ
1. 音楽的な「ズレ」と個性の衝突
Goose houseは、もともと「PlayYou.House」というプロジェクトから始まりました。ところが活動が長くなるにつれ、個々の音楽スタイルや表現したいことが、少しずつ噛み合わなくなっていったんです。
「全員でひとつの曲を作る」ことに限界が見えはじめ、リーダー的存在だった工藤秀平さんもメンバー間の調整に頭を悩ませていたとか。
2. YouTubeだけでは食べていけない?
Goose houseはYouTubeの再生回数こそ大きかったものの、収益のほとんどが原曲の権利者に分配される仕組み。総再生数が12億回を超えても、グループ全体の年収は約300万円とも言われています。
加えて、メンバー間の分配にも課題があり、「このままじゃ音楽で生きていけない」という現実が立ちはだかっていたのです。
3. ソロでやりたい気持ちが強くなった
Goose houseのメンバーは全員がシンガーソングライター。それぞれに「自分だけの音楽」を作りたい気持ちが強まり、グループ活動とのバランスに苦しむようになります。
たとえばマナミさんは、8年の活動を経てソロプロジェクト「PATCH VIDE」を立ち上げ、自由な音楽表現を追求しはじめました。
Play.Gooseが目指す、新しい音楽のかたち
2018年に立ち上がったPlay.Gooseは、こうした課題を踏まえ、自由で柔軟な音楽活動を目指す新しいスタイルです。
● メンバーは「流動的」、でもつながっている
工藤秀平、マナミ、ワタナベシュウヘイ、沙夜香がコアメンバーとして活動しながら、竹渕慶や竹澤汀といった元メンバーがときどき戻ってくるスタイル。
それぞれがソロで活動しつつ、必要なときに集まるという“音楽のシェアハウス”的な仕組みになっています。
● 収益源はYouTubeに頼らない
新たな試みとして、以下のような収益モデルを展開しています:
ファン向けアプリ「P.G@STAND ALONE」での月額課金 グッズやライブの直販 全国ツアーでのリアルなつながりづくり
特にワタナベシュウヘイさんは、2024年に47都道府県を巡るライブツアーを敢行。地域密着の活動に力を入れています。
● カバー中心から、オリジナル重視へ
かつてのGoose houseはカバーが主流でしたが、Play.Gooseはオリジナル楽曲の制作と挑戦的なサウンドに力を注いでいます。
沙夜香さんはエレクトロニカ風のソロアルバム『SHARE』を発表し、工藤秀平さんはロック色の強いK.K.でライブ活動を精力的に行っています。
今どうしてる?メンバーの“今”を追ってみた
● 工藤秀平
Play.Gooseの音楽監督。楽曲制作の中心人物 「K.K.」名義で年50本以上のライブを開催 noteで日々の気づきを発信する有料マガジンも運営中 手話通訳付きライブなど社会的意義のある活動も展開
● マナミ
2024年に新アルバム『FLICKER』を発表 年間100本以上のライブを開催し、ドラム演奏もこなす多才ぶり ソロ×バンドの両立で独自の音楽世界を構築中
● ワタナベシュウヘイ
竹森マサユキとの47都道府県ツアーを完走 自身のレーベル「Watanabe Records」を立ち上げ、後進の育成にも着手
● 沙夜香
ソロ活動「ポムの村」でピアノ弾き語りに専念 初ワンマンライブ「はじめトまして」開催予定(2025年6月) Play.Gooseではクラシック調アレンジで音楽の幅を広げています
ファンとの関係もアップデート
昔の「ハウスメイト」から、今は「旅する仲間」へ。
Play.Gooseは、ただ聴くだけではなく一緒に作り上げていく関係性を大切にしています。
たとえば、公式アプリではライブアーカイブの視聴や、メンバーへのリクエスト機能が充実。noteでの発信やSNSでの交流もあり、アーティストとファンの距離がグッと近くなりました。
Play.Gooseのこれから
現在、YouTubeからの収益は月に約5万円程度。それでも、彼らは「やりたい音楽」と「生きるための仕組み」を両立させるべく、こんな取り組みを進めています。
ライブでの収益最大化(少人数&高頻度の公演) アプリでの限定コンテンツ販売 企業タイアップなどの外部連携
音楽に情熱を注ぎながら、生きるための方法も自分たちで作っていく――それが今のPlay.Gooseなのです。
まとめ
Goose houseからPlay.Gooseへの移行は、ただの名前の変化ではありません。
それは、音楽でどう生きていくかを真剣に考え、模索し続けてきた結果なのです。
変化を恐れず、自分たちらしいやり方を見つけた彼らの今後が、ますます楽しみですね。